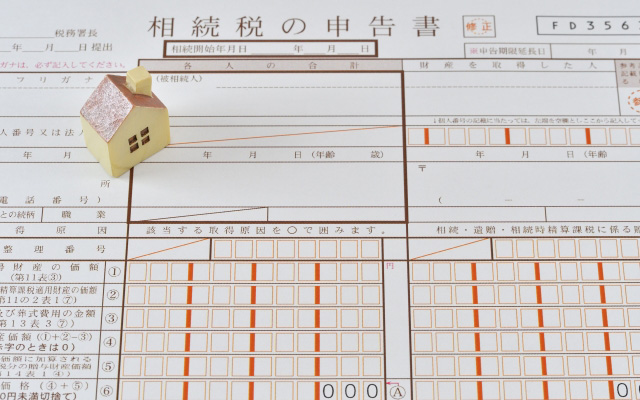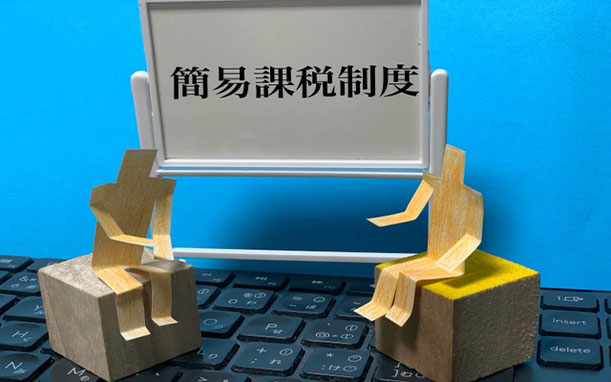03日 7月 2024
『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』とは、親や祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。 贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上の受贈者が対象です。...
カテゴリ:企業法務 · 03日 7月 2024
『業務改善助成金』は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資など(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)を行なった場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。 助成上限額および助成率にて算出した金額のうち、いずれか低いほうが支給されます。
カテゴリ:企業法務 · 03日 7月 2024
上場企業や大会社に整備が義務づけられている『内部統制』とは、企業が健全かつ効率的な事業活動を行うために必要な仕組みのことで、経営者や従業員が守らなければいけないルールでもあります。 内部統制の整備は中小企業にとって義務ではないものの、企業価値の向上や経営目標の達成にも大きく関わるため、積極的に取り組んでいくことが望ましいとされます。...
カテゴリ:企業法務 · 22日 12月 2023
消費税の申告の際には、売上にかかった受取消費税から仕入れにかかった支払消費税を差し引く『仕入税額控除』の計算を行います。 こちらは、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みがとられています。 しかし、すべての取引について控除額を計算するのは非常に手間と時間がかかります。...
カテゴリ:登記 · 22日 12月 2023
民法や不動産登記法の一部などが改正され、2024年4月1日から、これまで任意だった相続登記の義務化が始まります。 この義務化は、所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的としたもので、不動産を取得した相続人にその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務を課し、これに違反すると罰則を科すものです。...
カテゴリ:相続 · 13日 4月 2023
民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と定めています。 この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、被相続人のプラスの財産に限らず借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。...
カテゴリ:企業法務 · 13日 4月 2023
法人税の納付には、税金の前払いである『中間申告』が採用されています。 起業したばかりで最初の事業年度である企業や、中間申告時の納付額が10万円以下の企業などでなければ、中間申告を行って法人税を納付しなければなりません。 今回は、この中間申告の概要について解説します。
カテゴリ:登記 · 15日 3月 2023
不動産や法人の登記は、申請書を作成して登記所に提出する『書面申請』と、インターネットを介して申請データを送付する『オンライン申請』、そして、2020年1月から運用が開始された『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請』があります。 今回は、QRコード付き書面申請のメリットや、利用方法などについて紹介します。
カテゴリ:相続 · 20日 1月 2023
遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。 そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。 ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、紛失や偽造といったリスクがつきまといます。 また、相続人が遺言書の存在に気付かず、故人の意向が反映されない可能性もあります。...
カテゴリ:企業法務 · 20日 1月 2023
政府は、家計の安定した資産形成を図るため、個人による投資を促進しています。 2001年には個人型確定拠出年金の『iDeCo』(※名称は2016年から)、2014年には少額投資非課税制度の『一般NISA』、2018年には『つみたてNISA』がスタートしました。 それぞれ少額から始められ、運用益が非課税になるなどの優遇措置があるため、加入者数が増えています。...